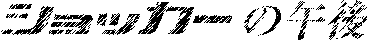
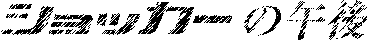
「余計な出費でしたね、少佐。」
「まあ、仕方なかろう。警察沙汰にでもなれば、今回の計画も水の泡、泡のお風呂はバブだからな。」
少佐と呼ばれた男は、傍らで電卓を叩いている男に言いました。
「それにしても、少佐もしっかりしてくださいよ。あんなところで高校生と事故ったりして…。あやうくライダーに気づかれるところだったそうじゃないですか。」
「その点は心配いらん、まさかライダーも我々が監視していたなどとは気づいておらんて。それにライダーの方には、わしもマリバロンも面が割れてないからな。まさに、灯台下暗しだよ、がはは。」
何を言ってるんだ、と男は思いましたが口には出さず、黙って出金伝票に『地獄大使』と署名し、本社宛の封筒に入れました。
「あれ、そう言えばマリバロンさんはどうしたんです?ここんところ、基地に戻ってこないみたいですが…。」
「ん、ああ、あやつは大阪にマンション手に入れたとか言ってたな。そのほうが計画に都合がいいそうだ。がはは、まさしく一朝一夕とはこのことだな、がはは。」
それを言うなら一石二鳥だし、それでも意味不明だぞと、男は思いましたが、黙って電卓を叩き続けました。
+++++
土曜日の晩、桜子を送っていった後、桃太郎峠を馴しをかねて5周ほど走りましたが、BMWは現れず、凶嫁舞はちょっとがっかりしました。翌、日曜日は朝から快晴で、大阪までツーリングにいくことにしました。一瞬、桜子を誘おうかなと思いましたが、座布団をつけられたDUCATIを想像し、ぶるるっと頭を振ると、デートは諦め、一人で行くことにしました。
玉島ICから山陽道に乗り、神戸JCTから中国自動車道に入るころには、DUCATIにもすっかり慣れ、右に左に車線変更を繰り返しながら、200km/hオーバーまで加速してみたりと、凶嫁舞はDUCATIの虜になりつつありました。吹田JCT手前で、ふとバックミラーを覗いた凶嫁舞は、はっとしました。後からバイクが追ってきています。それはぐんぐん迫り、みるまに凶嫁舞との距離を縮めてきました。そして、凶嫁舞の左側に並ぶと、速度を落としました。
+++++
BMWだっ。
+++++
白地に赤いラインの入ったレーシングカウル、銀色に輝くシリンダーヘッド、それはまさしく先日のBMWでした。
BMWのライダーは、並走するDUCATIのライダーが凶嫁舞だということに気づいたのか、彼の方へ顔を向け、にやりと笑うと、スロットルを大きく煽り、一気に加速を始めました。強大なトルクが時速150キロという速度にもかかわらず、BMWのリヤタイヤを空転させ、凶嫁舞の目の前で尻を振りダンスを演じてみせます。彼は負けじと、イタリアンVツインに喝を入れ、デスモドロミックエンジンの咆哮を悲鳴の領域まで上げながら、追走しました。
時速180キロ、190キロ、200キロ…、BMWの背後にぴったり張り付いたまま、いったいどこまで加速しつづけるのか見届けてやろうと、凶嫁舞はDUCATIにムチをいれます。時速210キロ、220キロ、230キロ…、イタリアンVツインの悲鳴は極限に達してしまったのか、タコメーターの針がレッドゾーンの真ん中あたりでピタリと止まり、同じようにスピードメータの針も進むのをやめ、それ以上の速度は無理のようでした。しかし、BMWはじりじりと離れていきます。いや、じりじりどころか、左手で小さくピースサインを作ると、一気に離れて行くではありませんか。
+++++
ええっ、マジかよ〜。
+++++
もはや、はるか前方の小さな点になってしまったBMWを見やり、くやしいよりも、あきれかえってしまうより他はなさそうな凶嫁舞でありました。
+++++
途中のSAで遅い昼食を取り、凶嫁舞が大阪に着いたのは、午後4時すぎでした。彼が、この大阪に来たのは、もちろんバイクで走りたかったからですが、日本橋に最近できたコンピュータのジャンク屋に寄ってみたかったということもありました。せわしく歩き回るヒトをかき分け、駅前の歩道にDUCATIを停めると、ポケットから雑誌の切り抜きを取りだし、店の場所を確認しました。店は汚い雑居ビルの地下で、所狭しとハードディスクやフロッピードライブが並べられ、怪しげなソフト類が積み重ねられていましたが、その一角に足のついた四角い箱がありました。ベージュ色の筐体に、なんとなく気を引かれ、近づいてみると6色に塗られた林檎のマークがついています。
「お客さん、スイッチ入れてもいいですよ。」
不意に店員に声をかけられ、凶嫁舞はぎくりとしましたが、店員に指さされたキーボードのスイッチに手を触れると…。
じゃ〜ん、と不思議な音楽が鳴り響き、小さな8インチの画面に「Welcome」の文字が浮かびあがりました。つづいて何やらヘンテコな絵と、矢印が現われ、それはまったく見たことのないモノでした。アルファベットしか刻まれていないキーボードからコマンドを入力しようとして、不思議なボタンのついた四角い箱がキーボードに繋がっているのに気づきました。
「これは?」
「マウスです。」
操作方法を教えてもらい、凶嫁舞はその面白さにすっかりのめりこんでいきました。
+++++
さんざんいじり回して、そのコンピュータの新型が入荷するというので、それを1台予約して、凶嫁舞が店を出たときには、日はすっかり沈み、あたりは真っ暗になっていました。駅前へ戻ろうと、細い路地を表通りに向かっていると、大きな声がしました。
「ざけんじゃねぇーよっ。」
声がしたのは一つ先のビルの陰からです。凶嫁舞は覗き込みました。暗い路地にネオンの光がうっすらと射して、全体が赤や紫にぼうっと霞んでいます。ふたつの人影が見えて、一人は黒い学生服、もう一人はOL風です。OLが何か話しかけたようですが、遠すぎて聞き取れません。学生服はいきなりOLをつきとばし、OLはその場にしりもちをつく格好で倒れました。さらに、学生服は手を上げて、殴りかかりそうです。凶嫁舞は、そうっと背後から近づき、
「おいっ。」
と声をかけました。学生服は驚いて振り向き、そのまま凶嫁舞に向かってきます。凶嫁舞は身構えましたが、意に反して学生服は凶嫁舞の脇を脱兎のごとく駆け抜けていってしまいました。ちらと見えたその横顔は、京谷太郎のようでした。
+++++
まさかな、こんなとこにいるはずないしな…。
+++++
「ありがとう。からまれちゃって、困ってたのよ。」
そう言うOLが立ち上がるのに手を貸した凶嫁舞は、驚きの表情を隠せませんでした。
「あら、あなた、こないだのバイク少年。」
OLは先日の事故の夜、病院で会った女性でした。
「半漁仁さんの…え・・と・・マリ…。」
「スニークス・バロン・マリよ。皆はマリバロンって呼んでるわ。」
そう言うと彼女は歩きかけ、二、三歩進んだところで脚をかかえてしゃがみこんでしまいました。
「大丈夫ですか?」
「脚をくじいちゃったみたい。手をかしてくれる。」
彼女に肩を貸し、腰に手を回して歩き出すと、ほのかな香水の匂いが漂ってきます。ふくよかな腰のあたりや、押しつけられた身体からは、まだ若い桜子と違って、成熟した大人の女性の感触がぷんぷんします。凶嫁舞の息が荒くなったのは、彼女を抱えて歩いてるせいだけでは、ないようでした。
表通りに出てタクシーを拾い、彼女が乗り込むと凶嫁舞は挨拶して帰ろうとしました。
「あ、待って。うちはここから近いのよ。送ってってくださらない?」
躊躇している彼を、マリバロンはなかば引きずり込むように、タクシーに乗せたのでした。
+++++
彼女の住まいは、大阪市内の高級マンションでした。賃貸だったにしても、おそらく、月額数十万円という家賃のはずで、とても一介のOLでは維持できそうにもないところです。いったいどういう仕事をしてるのか、聞いてみたい衝動にかられましたが、詮索好きと思われるのもいやだったので、足を引きずりながら歩く彼女に、凶嫁舞は黙って手を貸し、最上階の部屋へ入ったのは、午後8時を回っていました。
「じゃ、僕はこれで…。」
再び帰ろうとする凶嫁舞を、彼女は
「あ、お茶ぐらい飲んでいって。」
と引き止めます。たしかに今帰ったら、二度と会えないような気もしていた凶嫁舞は、それじゃ、とソファーに座ろうと戻りかけ、テーブルの脚につまづき、ちょうど立ち上がりかけた彼女に覆いかぶさるように倒れてしまいました。
「ああっ、すいませんっ。」
あわてて身体を引きはなそうとしましたが、彼女が凶嫁舞を羽交い締めにしているので動きがとれません。もがいている凶嫁舞の唇に、いきなり彼女の唇が押しつけられました。
+++++
わわわわわわ〜っ。
+++++
凶嫁舞はいきなりの展開に気が動転しました。が、身体は正直で下半身は熱くなっていくばかりです。その固くなった股間を彼女の指先でまさぐられ、彼の抵抗する力もぐっと弱まってしまいました。彼女は、いつの間にか巧みに自分のブラウスの前をはだけ、ブラのフロントホックを片手で器用に外していました。白い豊かな乳房があらわになり、彼女の呼吸に合わせゆっくりと上下動しています。彼女の指先は、ますます激しく凶嫁舞の股間を撫で擦り、凶嫁舞は頭がぼうっとして、彼の下半身は今にも爆発しそうでした。そして、彼女の形のよい大きな乳房、その頂点で屹立している乳首に凶嫁舞は手を伸ばし、おそるおそる触れました。
その瞬間です。凶嫁舞は、何か異質なものを感じました。そしてそれは底知れぬ恐怖に変わっていきます。まるで、底なし井戸の縁から地底を覗き込むような、あるいは、どこまでも落ちていくフリーフォールのような、真っ黒な闇に吸い込まれてしまいそうな恐怖です。制御不能なほど熱く固くなっていた彼の性器は、たちどころに萎え、背筋に悪寒が走りました。
「わわわ、お、俺、もう帰りますっ、すいませんっ。」
凶嫁舞は一度も後を振り返らず、一直線に廊下を突っ走り、エレベータが待ちきれず、一気に階段を駆け降りていったのでした。
一人、部屋に取り残されたマリバロンは、まだ固く勃起している乳首に触れ、ふうっとため息をつくと、すっと立ち上がり着衣の乱れを直しました。ついで、髪をかき上げながら、その悩ましいうなじを撫で、指先でそこにあるであろう刻印をたどったのでした。
+++++
あまりに夢中で走ったせいで、呼吸の乱れがようやく治まったのは、吹田JCTを過ぎたあたりでした。暗い高速道路で、DUCATIの頼りないヘッドライトは、前方をおぼろげに照らし出しています。凶嫁舞は、脳裏でゆっくりとあの部屋での出来事を反芻してみました。透き通るような白い肌、大きく盛り上がった胸、思い出すと未だにかあっと熱くなる気がします。それなのに例えようのない恐怖。いったいぜんたい、どうしたっていうのでしょう。あまりも相反する感情に、自分のとった行動に自信が持てなくなりました。
+++++
据え膳食わぬはなんとかって言うけど…。でも、なんか違う。そう、人間ではない何か…。蛇に睨まれた蛙になったような…。
+++++
今にも大きく口を開けた大蛇が襲ってくるようで、凶嫁舞はDUCATIのスロットルを煽ったのでした。
+++++
まったく、きょうかまいったらどこ行っちゃったのかしら。映画見に行こうと思って、電話したら出かけた後だし、さっき電話したらまだ戻ってないっていうし…。男の子にバイクは、ネコにマタタビと同じね、ホントに。
+++++
桜子は、ベッドに腰かけて、いつの間に撮ったのか、定期入れに入れた凶嫁舞の写真を、眺めました。遠くでバイクの音がしたような気がしましたが、すぐに消えてしまいました。桜子は大きくため息を漏らし、ベッドに仰向けになりました。
+++++
ホ〜ント、ニブいっていうか、カッコつけちゃってさ。あたしのコト、なんだと思ってンだろ。ヤんなっちゃうな。
+++++
ベッドのわきでカーテンが、ゆらっと動きました。桜子は、ふと気になって、上半身を起こすと、二階の部屋の窓を開けてみました。冷たい空気が一気に流れ込んできて、桜子はパジャマの襟元をつかみ小さく息を吸い込みました。通りの方に目をやると、寒そうにジーンズのポケットに手をつっこみ、こっちを見上げている男が街燈に照らしだされています。
+++++
きょうかまいだっ。
+++++
彼女はパジャマのまま、階段を駆け降り、勢いよく庭木戸を開け、道路に飛び出しました。
「よっ。」
凶嫁舞は左手を軽く上げ、うっすらと笑みを浮かべました。
「いつから、ここにいるの?」
「ん、今さっき。」
「バイクは?」
「ウルサイから、向こうの角に停めてきた。」
凶嫁舞が指さす方を、覗き込むように眺めていた桜子は、不意に抱きしめられ、どっきりしました。
「あ、きょうかまいぃ。」
「ごめん、しばらくこのままでいてくれ。」
暖かい桜子の柔らかい身体を抱きしめていると、張りつめていた気持ちがほぐれ、自分ではどうすることもできず、いつのまにか凶嫁舞の眼からは涙が溢れていました。
「きょうかまいぃ、泣いてンの?」
「ち、違うよ、寒くて鼻水が出てんだい。」
しばらく彼女の温もりを確認するかのように、無言のまま抱きしめていた凶嫁舞は、ようやく身体を離しました。
「どうしちゃったの? 大丈夫? ね、お茶でも飲んでってよ。」
「…いや、もう帰るよ。なんだか会いたくなっちゃってさ…。悪いことしたな。ごめん。」
「謝ることないよ…。」
心配そうに見つめる桜子をよそに、凶嫁舞はジャンパーのポケットからごそごそと白い包みをとりだしました。
「これ、おみやげ。」
「え、なに?」
包みを開くと、通天閣のキーホルダーが出てきました。
「ヘンなモノでごめん。」
「うぅん、ありがとう。」
桜子は、ちょっと背伸びをして、凶嫁舞にキスしました。
+++++
ぼんやりした街燈が、ほんの少しの間だけ明滅し、通りを渡ってくる風が桜子の髪を揺らしました。そしてDUCATIの排気音が聞こえなくなるまで、桜子はそこでそうして風に吹かれていたのでした。