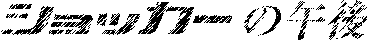
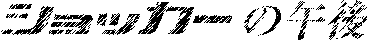
ランチャ・テーマ。フェラーリエンジンを搭載し、流麗なフォルムのラグジュアリークーペです。大人びた雰囲気を持つ外観とは裏腹に、水平対向8気筒エンジンは、どこまでもシャープに吹け上がり、トップエンドで奏でるフェラーリエンジン特有の金切り声が、深夜の第三京浜にこだましました。左ハンドルのランチャ・テーマを軽々と操るのは坂。ナビゲーターシートは空席です。マロは昼間の疲れからか、リヤシートで小さく丸まって寝ていました。二人は警視庁での記者会見の後、社には戻らず、二子玉川の坂のマンションへ行き、軽く食事をとり、クルマをマロのイスズから坂のランチャに替えて、横浜へ向かっているところでした。夏の夜ともなれば、第三京浜にも、ちらほらと暴走族が走っていましたが、それらを圧倒するスピードで坂はランチャを走らせました。日中と比べて涼しくなったとはいえ、夏の夜特有のもうっとした空気があたりを包み、ランチャが走り去った後の路面に渦を巻き、長く尾を引いていくようでした。
+++++
看護婦に注射されながら、我ながら間抜けな行動だったなと、MBXは思いました。重傷を負っているとはいえ、自ら息を止めるのは、さすがに限界がありました。2分間は我慢したのですが、あまりに苦しくなり、あきらめて呼吸を開始しようとしたら、なんと、息ができないのです。MBXは金魚のように、口をパクパクさせ、目からは涙が出ました。いやだ、死にたくないっ。目の前が真っ暗になりかけたとき、ようやく医師が駆けつけて、なにやら機械を調節すると、ようやく息ができるようになりました。ああ、生きててよかった。MBXはほっとすると、また涙が出てしまいました。
「えへへ・・。」
心配そうに見ている星野スミレと視線があってしまい、MBXは照れくさそうに笑いました。看護婦が行ってしまうと、また二人きりです。星野スミレ刑事は、MBXのフロッピーに入ってる画像を一枚一枚、黙って見ています。フロッピーにはジェイペッグ圧縮した画像が40枚入っていました。MBXは元々筆の早い方ではありませんでしたが、今回の作品集には思い入れもあって、仕事の合間に寝る間も惜しんで、着色まで含めて一気に描ききったものです。刑事とはいえ、彼の作品を見てもらっているお客さんです。MBXは評価が気になりだしました。星野スミレ刑事は、綺麗で丁寧に描かれたイラストに見入っていましたが、いつのまにか彼女をじっと見つめているMBXに気づきました。
「…落ち着いたみたいね。」
星野スミレ刑事が微笑みかけました。
「ど、どれが一番良かった?」
MBXは思い切って聞いてみました。
「そうね。7番と23番かな。あと、看護婦さんの格好した天使? あれはなかなか綺麗だったな。絵夢美くんは、イラストレータ目指してるの?」
「い、いいえ、マンガ家なんです、っていっても、今は会社員ですけど…。」
「そう。…ね、この絵、モデルがいるの? 何枚か同じ女のヒトを描いてるみたいだけど。」
そう問い掛けられて、MBXはしまったと思いました。あのフロッピーには、フランスから赴任してきたイオットさんをモデルに、想像しながら描いたイラストが相当な枚数あったのです。
「…い、いや、空想ですよ。マンガ家ですから、それくらい、か、簡単なんです…。」
MBXの答えに、星野スミレ刑事はそれ以上気にする様子もなく、次のページをめくっています。あまり言及して余計な事聞かれてもまずいので、MBXはさりげなく話題を変えました。
「け、刑事さんは、どうしてここにいるんですか?」
彼女は画面から目を話さずに答えました。
「それは、あなたが目撃者だから。」
「で、でも、僕は何も見てないかもしれないし、喋らないかもしれないですよ。」
彼女はちょっと小首をかしげ、パワーブックを閉じると、MBXの方を向きました。大きな瞳と長い睫毛が印象的です。MBXはドキリとし、病室の奥の心電図計がピッピッと少し早くなったような気がしました。
「ほんとは言いたくないんだけど、教えてあげましょう。あなたが話す、話さないは関係ないのよ。目撃者として、此処にいるっていう情報が大事なの。目撃者が生きているとなれば、動き出す輩が必ずいます。私たちは、それを待っているのよ。」
「え、それじゃあ、僕はおとりですか…。」
「ま、ちょっと違うけど、そんなところ。…ああ、心配しなくても大丈夫。此処の警備は万全よ。警官20人で固めているから、スタローンでもなければ、突破はできないわよ。」
MBXは複雑な心境でした。おとりということは、話す、話さないなんて問題より、実際は彼自身の生死さえ関係ないということですから。
心配そうな表情のMBXを見て、星野スミレは立ち上がりました。
「大丈夫、スタローンがきても、私を倒すことはできないわよ。」
そう言うと、彼女は上着を脱ぎました。小柄な感じでしたが、胸はぐっと大きくブラウスを高々と持ち上げています。肩からホルスターが下がり、左のわきの下に大型の自動拳銃が1挺、短いスカートの腰のベルトの右側に、リボルバーが1挺ぶら下がっています。
「ここは、秘密よ。」
彼女は微笑しながら、片足を椅子にのせるとスカートをめくり上げ、太股の内側を見せました。そこには、さらに1挺、小さな拳銃が収まっていました。
「どう? 安心した?」
MBXは彼女のスカートの奥を覗き込んだまま、ぴくりともしません。
「…絵夢美くん? …ね、ちょっと…あら、やだ…ちょっと…せ、せんせえぇぇぇぇっ、だ、だれかぁ、看護婦さーんっ、…このヒト鼻から血、流してますーっ。せんせーっ。」
+++++
根津藤衛は自転車を自転車置き場に停め、鍵をしっかりかけました。クルマぐらい与えてくれてもいいのに、とひとりごとを呟きながら病院の裏手に回り、デイパックから猫を取りだしました。
「では、お見舞いに行ってこい。」
そう言い聞かせ、猫を放します。すると、猫は半開きの裏口から建物の中にすうっと入っていきました。それを確認すると、根津は裏庭の大きな木をするすると登りはじめ、二股になっているところに腰を落ち着けました。そして、大きく息を吐き出し、目を閉じると深い瞑想に入りました。次第に猫の視界とシンクロしていきます。裏口から救急病棟を抜け、階段を上がります。所々に警官がいました。見つからないよう注意しながら、ゆっくり歩を進めます。外科病棟という案内看板が見えました。すでに猫と一体化した根津は、慎重に廊下を進んで行きます。集中治療室の看板を見つけましたが、入口には厳重な扉があるうえに警官が多すぎます。猫となった根津は後ずさりし、物陰に身を潜めチャンスを伺うことにしました。
+++++
医師は首をひねり、考えこんでいます。
「おかしいなあ、脳障害はないんだけどなあ。どうして、鼻血が出たんだろう?」
MBXは恥ずかしくて、耳まで真っ赤になりました。星野スミレ刑事は、まさか自分のスカートの中を見せたら鼻血が出ましたとも言えないので、病室の隅で知らん顔してます。しばらくあれこれ悩んでいましたが、とりあえず様子を見ましょうと言って、医師は出ていきました。医者が出ていくと、星野スミレがベッドに近づいてきて、ぺこりと頭を下げました。
「ごめん。あんまり免疫がなかったのね。また輸血するところだったわね。」
MBXは何と答えたらいいのかわからず、まだまだ修行が足りないなあと、ため息をつきました。
時計はそろそろ深夜12時を回ろうとしていました。星野スミレ刑事は、定時連絡の時間だから、と病室を出ていきました。病室はクリーム色の壁に合わせて、医療機械もクリーム色に塗られています。ピッピッと小さな音を立ててMBXが生きてることを何処かの部屋へ伝えている機械やら、いったい何の装置だか想像もつかないような機械、何十本ものチューブとコードが複雑に絡み合い、まるで映画に出てくるクレージードクターの研究室のようです。MBXは首をゆっくり回して、病室を観察しました。廊下側から部屋の中をぐるっと見回し、反対側の窓まで辿り着いたとき、何か光るものを見たような気がして、もう一度視線を戻してみました。それは、天井の換気口でした。天井には、エアコンの吹き出し口とは別に、換気口のガラリが取り付けてあって、そこの奥から光がちらりちらりと見えるようです。MBXは気になって、じっと見ていると、今度はカリカリと金属を引っ掻くような音が聞こえてきました。音はだんだん大きくなり、やがてガタンと換気口のガラリが落ちてきました。ガラリがなくなり、換気口は、クリーム色の天井にぽっかりと開いた闇の入口のようです。その闇の奥に青白い光が見え隠れしています。青白い光はゆらゆらと揺らめき、低いふぅっという唸り声を発しています。MBXは恐くなり、声を上げようとしました。その時、青白い光は闇の入口から飛びだし、MBXめがけ襲いかかってきました。
+++++
病院のロビーには、さすがに報道陣も引き上げたのか、ほとんど人影は無く、待合室の椅子に数人が横たわっているだけでした。星野スミレはポケットから小銭を出すと、公衆電話に入れダイヤルしました。
「はい、強行2課です。」
受話器から聞きなれた声がしました。
「あら、凶嫁舞。なんで署に戻ってるの?」
「あ、星野かあ。丸の内の会社、動く様子がないんで、交代して帰ってきたんだ。そっちは、どうだい?」
「こっちも変化なし。ちょっとドタバタしたけど…。」
話しながら、星野スミレはあたりを見回しました。誰か2階から降りてきたようです。看護婦でした。照明が落としてあるので、顔は良く見えませんでしたが、見覚えがある感じです。背が高く、すらっと伸びた手脚、大きく張りだした胸。どこかで見たような気がしましたが、思い出せません。つい最近会った気がするのですが…。
「…おい、どうした。聞いてんのか?」
電話口で凶嫁舞に言われ、我に帰りました。
「…聞いてるわよ。夜明け前には交代に来てくれるんでしょうね。」
「おお、後3時間少々だ。それまでよろしくな。」
星野スミレは電話を切ると、気になってさっきの看護婦の後を追いましたが、すでに見当たりませんでした。
+++++
換気口から落ちてきた物体は、音も立てずにふわりとMBXのベッドに着地しました。MBXからはチューブやら機械が邪魔で姿がよく見えません。物体はゆっくりと1歩1歩、MBXの胸の方へ近づいてきます。
「にゃあ。」
突然、その物体が鳴きました。猫です。天井から降ってきたのは、真っ黒い猫でした。
「な、なんで、猫が…。」
不思議に思いましたが、MBXは猫とわかってほっとしました。猫は慎重にMBXの体を登り、顔の前まで来ました。
「にゃあ。」
また鳴きました。そして、MBXの顔を舐め、一瞬ごろごろと喉を鳴らしたような気がしましたが、次の瞬間、大きく口を開けるとその牙を剥き出し、MBXの喉に噛みつきました。
「ぐえ…ごふっ。」
MBXの口から鮮血が吹き出します。MBXはなんとか振りほどこうとしますが、いかんせん体がいうことをききません。猫は、一度でけい動脈まで牙が届かず、一旦MBXの喉から顔を離しました。息を整え、もう一度大きく口を開いた刹那、病室のドアを開け、看護婦が入ってきました。猫は、にゃあと鳴くと、体の向きを変え、看護婦に飛びかかろうと身構えました。全身の毛を逆立て、低くふーっとうなり声をあげます。猫の体が変化しはじめました。前脚の爪が長く伸び、金属の光沢を見せます。牙はますます大きくなり、まるで小型のサーベルタイガーのようです。そして猫は、全身をばねにして高く飛び上がりました。猫のねらいでは、看護婦の喉元へ飛び込んだつもりでしたが、彼女の動きの方が速かったようです。彼女は素早く腰をかがめると、椅子に置いてあったパワーブックを掴み、飛んでくる猫の鼻っ柱に叩きつけました。ぐしゃりと鈍い音がして、猫の頭蓋骨が砕け脳漿が飛び散りました。そして、そのまま床に力なく落下すると、動かなくなりました。
「坊やっ、大丈夫っ。」
騒ぎに気づいて、医者や看護婦が駆けつけてきました。誰かがMBXの手を握っています。それは、暖かく、柔らかく、なんだかMBXは妙に心が安らぐ感じがしました。
+++++
根津は頭部に強烈な痛みを感じ、ふらついて木から落ちてしまいましたが、彼は器用に体をひねると、柔道の受け身のようにくるりと回りました。
「く、くそ。誰だ。邪魔しやがって。」
根津は唸りました。
「さっきの攻撃では、まだ致命傷までいかなかった。おのれ、こうなれば秘技キャットストリームだ。」
根津は仁王立ちになり、両腕を天高く掲げました。彼の全身を黒い毛が覆っていき、大きな黒豹へと変身していきます。そうです。彼はショッカーの改造人間、黒豹男だったのです。黒豹が、がううと夜空に唸ると、何処からともなく、猫が集まってきました。猫たちは、皆猫にあるまじき巨大な牙と鋭い爪を生やし、黒豹を囲むようにぞろぞろと病院の裏口へ向かっていくのでした。
+++++
「何があったのっ。」
星野スミレは自分が電話をかけに行ってる間に、参考人が殺されそうになったと聞いて、少々慌てていました。
「とりあえず、出血は止まりました。傷はそんなに深くないから、命に別状はありませんよ。」
医者が再三の呼びだしに半ばあきれながら言いました。
「それで、犯人はっ?」
後片づけをしている警官が、床にころがっている猫の死体を指さしました。
「猫? …猫に咬まれたっていうの…?」
「はあ、猫です。猫が入り込んで、参考人を襲ってたそうです。」
警官は申し訳なさそうに、星野スミレに言いました。まったく、猫の子一匹通すなって言っておいたのに、この警官どもときたら…、星野スミレは警官達を睨みつけました。
「…こちらの看護婦さんが助けてくださったそうです。」
恐縮しながら警官のひとりが、MBXの手を握っている背の高い看護婦を指しました。星野スミレが礼を言う前に、看護婦が口を開きました。
「あなたのミスよ。」
何をっと思いましたが、その通りです。ほんの4、5分とはいえ、誰かを代わりに配置すべきでした。とはいえ、あまりにずばり言われたので、むっとした星野スミレは、ぷいとそっぽを向きました。そして、血にまみれ床に落ちているパワーブックに気がつき、拾い上げようとした手が止まりました。
「治療が終わったなら、皆出てください。」
急に星野スミレが声を荒げます。医者や看護婦が顔を見合わせながら、出ていく中から、先刻の背の高い看護婦だけを呼び止めました。他のものが全員出たのを確認すると、星野スミレは後ろ手でドアを閉めました。
「まんまと騙されるところだった。」
星野スミレは看護婦に言いました。看護婦は何も答えません。
「さっきロビーで見かけたとき、気づくべきだった。これは、あなたね。」
そう言うと、星野スミレはパワーブックの液晶パネルを開きました。パワーブックは先程の衝撃で液晶にひび割れが生じていましたが、それでもなんとかMBXの描いたイラストを映し出しました。看護婦の格好をした天使。それは、星野スミレの目の前に立つ看護婦とあまりに酷似していました。短い金髪にナースキャップを載せた、青い瞳の天使。
「あなたは誰?」
「誰でもないわ。ただの看護婦よ。」
「あなたが、彼を殺そうとしたんでしょう。」
「…犯人は猫だって言ってたじゃない。」
「猫が? 馬鹿言っちゃいけないわ。猫が一匹で此処まで来て、喉笛に咬みついたりしない。」
星野スミレはそう言いながら、ホルスターから自動拳銃を抜き、看護婦に狙いを定めました。看護婦は驚きもせず、冷めた目で彼女を見ながら
「また、ひとつミスよ。」
と言いました。
「なんとでも、おっしゃい。あなたを逮捕します。」
星野スミレは銃を突きつけたまま、看護婦を後ろ手に手錠をかけ、手錠をベッドに固定しました。そして、椅子に座ると、銃は構えたまま、問いただします。
「私は、公安庁の星野スミレ。あなた、名前は。」
看護婦は、何か言おうとしましたが、途中でやめ、大きく溜息をつくと
「イオット、有賀イオット。」
そう名乗りました。
+++++
病院のロビー。待合室の椅子で、何人かの報道陣が寝ているはずでしたが、その寝息すら聞こえません。それもそのはずです。彼らには、全員首がありませんでした。彼らが寝ている場所から血の後が点々とつづき、階段を上がっていきます。2階から悲鳴が聞こえてきます。
「ひ、ひえー。」
警官の1人が腰を抜かしながら、震える手で銃を握っています。彼の銃口の先には、血の滴る首をくわえた、大きな黒豹と何百という猫の大群がいました。
「にゃあ。」「にゃあ。」「にゃあ。」
警官は銃を撃つ間もなく、たくさんの猫に襲いかかられ、絶命していました。夜明けまであと2時間。星野スミレにとって、遠い夜明けとなりそうでした。