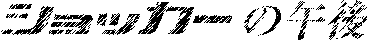
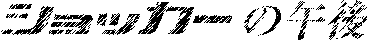
学校の授業なんてものは、おおむね退屈で、でも時に興味深い話が出て、それでいて何か心にひっかかると、授業を逸脱して思考の谷間に潜り込むというのが、凶嫁舞の日課で、それに彩りのスパイスとして、たまに試験がやってくるものだと思っていました。今週も同じように過ぎていき、おきまりの抜き打ちテストがあって、生徒達は驚いたふりをしながら黙々とこなし、先週と少し違うのは、表に出ると寒くなってきたことと、凶嫁舞が桜子と同じ電車で帰るようになったことくらいでした。
金曜の夜は、土曜の夜に映画を見に行く約束をして、桜子とは駅で別れ、そして今朝、土曜日の朝の教室です。コピーしたような時間の繰り返しのはずでしたが、それは微妙に違っていました。凶嫁舞が教室に入ると、教室がやけに静かなのに気がつきました。不審に思いましたが、その理由はすぐ分かりました。京谷太郎とその取り巻き連中がいなかったのです。まあ、彼らが居ようと居まいと、凶嫁舞には関係なかったのですが、不良の割りには皆勤賞の彼らが、そこに居ないのは、たしかに珍しいことではあったかもしれません。
凶嫁舞が、教室の奥、窓際の一番後の席に座ったとき、もうひとついつもと違うことが分かりました。彼の前の席に座っているはずの、桜子がいなかったのです。
+++++
おかしいな、夕べは元気だったけど…。
+++++
結局1時限目には彼女は顔を出さず、なんとなく嫌な予感がして、凶嫁舞は彼女の家へ電話してみました。心配で電話してる割りには、母親が電話に出たらどうしよう、なんて余計なことまで考えていましたが、受話器は呼び出し音が鳴り続けるだけで、誰も電話に出る気配はありませんでした。受話器を置き、教室へ戻る途中で、鼻に白いギプスをつけた生徒とすれ違いました。先週、彼が痛めつけた京谷の取り巻きです。鼻の骨が折れていたようです。
「おい。」
凶嫁舞が声をかけると、彼は驚いたように飛び上がり、一目散に走って逃げてしまいました。
不思議に思いながらも、凶嫁舞は教室に入り席につくと、机の上に封筒が置いてありました。宛名も差出人も書いてありません。封筒の中には便箋が一枚。
『裏の川原で待つ。染井桜子は、俺が預かった。京谷太郎』
まさしくそれは、今日がいつもと違う最大の理由と言えたでしょう。凶嫁舞は脱兎のごとく駆け出し、教室を飛び出していきました。
+++++
「さそり男の居場所は分かったのかね、地獄大使。」
「はあ、少佐。それが、夕べまでは分かっていたのですが、今朝になったら、とんと…。」
「ばかもの。とんと、じゃないぞ。トントはハリーの友達だ。まったく大事な作戦決行日だというに、肝心の改造人間がおらんでは、話にもならんわっ。」
半漁仁はいらつき、机を叩きました。
「改造手術を受けると、精神力が未熟な場合、制御不能になることは、よくあることだわ。」
奥のソファーに腰をおろしていたマリバロンが言いました。
「我々だけで、決行しましょうか…?」
電卓を叩きながら、地獄大使が恐る恐る言いました。
「それは、無理ね。今回の作戦は、隠密裏にコトを運ぶ必要があるし、そのために、さそり男の特殊能力が必要だったのよ。」
「くそ、わざわざ目標の米軍基地に忍び込みやすいように、隣の高校から人選したっていうのに、よりによってバカを選んでしまうとはなっ。」
「え、一番ワルそうだから、あいつにしろって言ったのは少佐ですよ。」
「えぇい、うるさいっ。とにかく、さそり男を捜し出すんだっ。それまで帰ってくんなよっ、地獄大使っ。まったく、門前の小僧、習わぬ経を読む、だわいっ。」
地獄大使は、なに意味不明なこと言ってるんだと思いましたが、階級は少佐の方が上でしたから、おとなしく秘密基地である倉敷ビル3階ブラジル商事を後にしました。とは言っても、捜すあてなどありませんから、通りを渡って向かいの喫茶店に入り、インベーダーゲームの最終ステージをクリアすべく100円玉を投資し続けたのは言うまでもありません。
+++++
玉島川、一級河川に指定されてはいますが、台風の時に氾濫する以外、これといって特徴もない河です。ちょうど凶嫁舞の学校の裏手で大きく曲がっているので、岸に大きな洲ができていました。その真ん中あたりに一本の木が生えていて、その木の根元に京谷はいました。黒い学生服に、学生帽を目深に被り、左手には木刀を持っています。
「京谷っ、桜子さんをどうしたっ。」
凶嫁舞は堤防の上から、大声で怒鳴りました。
「さあ、どうしたもんだかな。取り返したければ、俺と勝負しろっ。」
言われるまでもありません。凶嫁舞は堤防からジャンプすると、京谷めがけて走り出しました。夏の間はその生命を謳歌したであろう、背の高い雑草がここのところの寒さで枯れ、あたりを黄金色に染めつつありました。その枯れ草の中から、突然黒い学生服を着た男たちが飛び出し、凶嫁舞の行く手を遮りました。
「えぇい、邪魔するなあっ。」
凶嫁舞は手近の男からなぎ倒し、当たって砕けろとばかりにパンチを繰り出しました。
「きょうかまいパ〜ンチっ。」
ちぎっては投げ、ちぎっては投げ、凶嫁舞に近づく男たちは、まるでスーパーボールのように宙を舞っていきます。しかし、驚いたことに、一向に数が減る気配がありません。逆にどんどん増えている気さえします。息が切れ、殴り続けた拳は血まみれです。最初、黒い学生服とばかり思っていましたが、よく見ると男たちは黒いタイツのような衣装に、黒いデストロイヤーばりのマスクをつけています。そして口々に『イイッ』と妙な雄叫びを上げながら、倒されても倒されても、立ち向かってきます。さしもの凶嫁舞も疲れ始め、周りを取り囲まれ、命運つきたかに思えてきました。
+++++
ああっ、桜子さんっ。
+++++
その時です。黒い衣装の男たちが、凶嫁舞のパンチの倍以上の高さで、空に吹き飛ばされていくではありませんか。振り向くと、パンチパーマが伸びてしまったような髪型の、眉の太い男が、男たちをなぎ倒していたのでした。
「少年、ここは俺にまかせろっ。」
男は野太い声で、凶嫁舞に声をかけました。男のパンチは凄まじく、はじき飛ばされた黒覆面たちは、河を飛び越え向こう岸まではね飛ばされ、あるいは地面深くに突き刺さり、たちまち、『イイッ』という雄叫びは小さくなり、残るは京谷だけとなりました。
「京谷っ、覚悟しろっ。」
凶嫁舞は高々とジャンプし、急角度でドロップキックをお見舞いしまいした。
「きょうかまいキ〜ック。」
驚いたことに、京谷は避けもせず、真正面から凶嫁舞のキックを喰らい、もんどり打って倒れました。
「京谷っ、桜子さんを返せっ。」
目深に被っていた帽子をひっぺがすと、現れたのは、白い鼻ギプスでした。
「あ、貴様、京谷じゃないなっ。京谷はどこだっ。」
「…へっ、へへへへ。今頃、京谷さんはお楽しみの最中よっ。」
「し、しまった、おとりだったのかぁっ。」
凶嫁舞は腹立たしくなり、男のギプスに思いきりパンチを見舞いました。ぼきぼきぼきっとニブイ音がして、男はぎゃっと言ったきり、白目をむき悶絶してしまいました。
「少年、大丈夫か。」
もじゃもじゃ頭の男が駆けつけてきました。
「…僕は大丈夫です。でも、桜子さんが…、僕は彼女を助けなければならないんですっ。」
「なにっ、人質を取られているのかっ。よしっ、私のバイクに乗れっ。」
彼が指さす堤防の上には、BMWが停められていました。男はヘルメットを凶嫁舞に渡すと、自分はノーへルのまま、バイクに跨がり、エンジンをかけました。水平対向ツインエンジンの排気音が炸裂します。
+++++
はっ、このBMWは…。
+++++
白地に赤いラインのカウル、タンクについたエンブレムは大文字のRにバイクらしき絵。
「あ、あなたは…。」
「いつぞやは、悪いことしたな、少年。」
男は右手を大きく捻り、凶嫁舞を後に乗せ、砂塵を巻き上げながら、BMWを走り出させました。
+++++
「少年、どこへ行ったらいいっ?」
「と、とりあえず彼女の家へっ、倉敷市内ですっ。」
「よし、わかった。」
男はBMWを国道に載せ、一気に加速しました。舗装のよい3車線の国道とは言え、昼間のこの時間そこそこの交通量はあります。なのに、BMWは車速をぐんぐん上げ、200km/hを超えてしまっているようです。前方を走るクルマがバックしているように見え、ものすごい勢いで近づいてきますが、男はブレーキもかけず、軽やかにBMWを操り次から次へとクルマを抜き去っていきます。凶嫁舞は振り落とされまいと、必死にしがみつきながら、男に道順を指示します。
「おじさんっ、次の交差点を右折っ。」
BMWは信号の色には構わず、物凄い勢いで交差点に突っ込み、前後タイヤを大きくドリフトさせながら曲がって行きます。歩行者の二、三人は跳ね飛ばしそうな勢いで、あっという間に桜子の家に到着しました。
「おじさん、ありがとうっ。」
凶嫁舞はバイクを飛び降り、開いたままの庭木戸をくぐって、玄関に駆け込みました。家の中は真っ暗で、事故の時と同じ臭いがしました。見ると廊下は赤く血で染まっています。流れ出た血を辿っていくと、台所に倒れている人がいます。あわてて駆け寄った凶嫁舞は抱き起こそうとして、愕然としました。その死体には、首がなかったのです。首は少し離れた冷蔵庫の前に転がっていました。桜子ではありません。母親のようです。叫び声を上げそうなのを無理矢理こらえ、二、三歩後ずさりすると、何かを踏みつけました。ゆっくり振り返り、それが父親の死体だと気づくまで、何秒もかかりませんでした。
その時、二階から声がしました。
「凶嫁舞、よく来たなっ。少し遅かった、お楽しみはもう始まってるぜ。」
その声はくぐもってはいましたが、京谷の声です。
「京谷ーっ、貴様よくもっ。」
凶嫁舞は階段を駆け登り、桜子の部屋の扉を思いきり開けました。そして、部屋の中の光景を見た途端、凶嫁舞は一歩も動くことができませんでした。
+++++
カーテン越しに差し込む薄暗い光の中に、素裸の京谷が居ました。そして、その前に桜子はこちら向きにひざまずかされています。衣服を剥ぎ取られ、猿ぐつわを噛まされ、両腕は後ろ手に京谷に掴まれたまま、凶嫁舞を見上げた両目からはとめどなく涙が溢れています。その白い肌には、京谷がつけたのか幾本かの傷がつき、滑らかな彼女の臀部には、京谷の腰が押しつけられゆっくりと前後していました。京谷は桜子の両腕を大きく引っ張り、堪らず彼女の上半身が反り返りました。彼女の柔らかい乳房が揺れ、苦痛の声が漏れました。
「きょ、京谷、貴様〜っ。」
凶嫁舞は拳を固め、一歩踏み出しました。
「おおっと、凶嫁舞、動くんじゃねえ。この女、どうするも俺様次第なんだぜ。」
京谷は不気味に笑い、なおいっそう強く桜子の腕を締めつけました。京谷の笑い声は次第に高くなり、あんまり笑いすぎたのか、顔が赤黒くなっていきます。いいえ、顔だけではなく全身がどす黒い赤色に変わり、桜子の腕を掴んだ手は、親指と人さし指の間が裂け始め、彼の尻からは背骨が突きだし、長く伸びていき、まるで尻尾のようです。京谷はみるみるうちに、変形し、いまや巨大なサソリになっていました。京谷は巨大なハサミと化した腕を振り回し、凶嫁舞を威嚇しました。両腕を離された桜子は、気絶しているのか、頭を床につっぷしたまま、サソリとなった京谷の下腹部から飛びだしている棒のようなモノに股間を貫かれて、そのかわいい尻だけが高々と持ち上げられています。
「この化け物めっ。」
凶嫁舞はヘルメットを脱ぎ、京谷に投げつけました。京谷はカチカチ音を立てるハサミで振り払います。そこにちょっと隙があったのを、凶嫁舞は見逃しませんでした。彼は、京谷の頭を飛び越し、背後に回り込むと、サソリの尻尾の生え際、ちょうど両足のつけ根あたりを思いきり蹴り上げました。
ぐしゃり。
何かが潰れるような音がして、京谷は大きな言葉に成らない声を上げました。
「ぐおぉおおぉぉおおぅおぅおうお〜っ。」
サソリの下腹部から伸びていた棒が縮まり、桜子がようやく開放され、ぐったりと床に倒れました。
「桜子っ。」
凶嫁舞はあわてて抱え上げ、名前を呼びました。京谷サソリは相当痛かったのか、うずくまり狂ったような声をあげていましたが、やおら立ち上がると、大きなハサミで、桜子を抱えた凶嫁舞を跳ね飛ばしました。それは凄い力で、凶嫁舞は二階の窓を突き破り表へ飛びだしてしまい、せめて桜子を傷つけまいと、身体を入れ替えるのが精一杯でした。凶嫁舞はいやというほど、地面に背中を打ち、そのまま意識が混濁していきました。最後に、『変身』という声とともに、何者かが二階に飛び上がって行ったような気がしましたが、定かではありませんでした。
+++++
冬が本格化したのか、吹きつける風は冷たく、メインジェットを5番ほど上げたのに、デロルトのキャブはぐずり続け、DUCATIは本調子にはほど遠い感じでした。平日の夕方、桃太郎峠には、走るクルマもなく、遠く街の喧騒が時折風に乗って聞こえてくるだけです。凶嫁舞は、泣き続けるDUCATIのエンジンを止め、胸ポケットからガムを一枚取りだし、口の中へ放り込みました。ほどなく聞き慣れた水平対向2気筒の爆裂音が近づき、BMWが駐車場に現れました。BMWのライダーは、ゆっくりと凶嫁舞のそばまでバイクを近づけると、キーを回しエンジンを停止させました。ヘルメットを脱いだ男は、何も言わず、ポケットから取りだしたマルボロに火をつけ、白い煙を吐きだしました。
もうあれから1ヶ月近く経過しています。結局あの後、凶嫁舞が気づいたときには、京谷は首がおかしな方向を向いたまま、地面に倒れていて、すでに息はありませんでした。警察の取調に凶嫁舞は真実をそのまま話しましたが、信じてもらえず、検察の作ったストーリーに基づく調書に署名せざるを得ませんでした。事件は、被疑者死亡のまま強盗殺人事件として取り扱われ、凶嫁舞は身を挺して恋人を救ったヒーローとして一時週刊誌の取材なども来ましたが、それもしばらくの間だけでした。
「桜子さん、どうだい?」
BMWのライダーがたずねました。凶嫁舞は首を振り、答えました。
「いいえ、相変わらずです。僕が行くと、泣いて暴れるんです。」
桜子は事件のショックが元で、固く心を閉ざしたまま、何の反応も示さない、無反応症になってしまい、ずっと病院に収容されたままでした。ただ、凶嫁舞を見ると暴れたり、泣いたりするので、医者は刺激治療になるかと、時々彼を面会させるのですが、つらそうに泣く桜子を見ると、凶嫁舞は心が締めつけられる思いでした。
「もう行かない方がいいのかもしれない…。」
「そんなことはない、いつか良くなるさ。」
その後は言葉も途切れ沈黙が続き、どちらからともなく、バイクのエンジンをかけました。先に頭を出口に向けたBMWに続いて、凶嫁舞もDUCATIを出口のラインに並べます。さっきまで、あんなにぐずっていたデロルトキャブは霧が晴れたかのように、雄々しく吸気音を響かせています。合図も何もなく、二台のバイクはスルスルと加速し、そして大きな爆音を山にこだまさせながら、走り出し、コーナーの向こうに消えて行きました。
+++++
+++++
「…というわけで、作戦の失敗の責任を取って、少佐はパラオ支店へ左遷。マリバロンさんと地獄大使さんは、本社経理勤務ってことになったのさ。」
勝義はMBXに、得意そうに話しました。
「かつよし〜、お前、社内の事情に詳しいなぁ。そいでさ、その作戦ってどんな作戦だったんだい?」
「さあ…、なんたって秘密作戦だったからねえ。そいつは、『花の後も春の情けは残りけり』ってやつよ、わっははは。」
MBXはなんだか意味不明でしたが、勝義が笑うので、いっしょに声をあげて笑いました。
+++++
+++++
-------エピローグ-------
+++++
まだ夏の日差しは残っていたと見えて、歩道に立つ凶嫁舞を容赦なく照らしつけていました。その日差しを反射して、銀色のヘッドカバーがきらきらと輝き、磨き上げられたクロームのきらめきが、白地に赤いラインのカウルをひきたたせます。
+++++
BMWか…。
+++++
バイク屋の店先に置いてあったBMWをしげしげと眺めていた凶嫁舞は、星野スミレの呼ぶ声に、古い記憶から呼びもどされました。
「きょうかまいぃ、次行くわよっ。」
「はい、はい、ただ今。」
走り出しながら、見上げた看板には『タチバナ・モータース』と書かれていました。