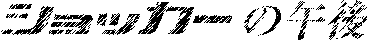
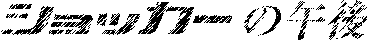
開いた窓から、晩秋の気配が静かに流れ込んできました。へたくそな字で書きなぐったノートが、ぱらぱらっとめくれ、自分がぼんやりと空を眺めていたことに、凶嫁舞信玄は気づきました。
視線を下におろすと、気の早い野球部員がそぞろランニングを始め、サッカー部との場所とり合戦に負けまいと、道具を広げはじめています。グラウンドの向こうに背の高い一種異様なフェンスがあり、銀色に光るポールに星条旗がはためいています。米軍玉島キャンプ。情報部が置いてあるとの噂で、基地内にはベージュ色の四角い建物がひとつきり。正門から入って、右手にヘリポートの模様が書かれていますが、そこにヘリが停っているのを凶嫁舞は見たことがありませんでした。
いつのまにか、授業は終わっていたようで、クラスメートたちは、さんざめき、荷物をまとめて帰り支度になっていました。
「きょうかまい〜、なにボンヤリしてるのよぉ。」
クラスの中では、美人の部類に区分けされている染井桜子が話しかけてきました。
「…ん、あぁ。」
凶嫁舞はのろのろとした動作で机の上を片付け、何冊かの教科書をデイパックにしまうと立ち上がりました。
「あんた、京谷さんたちに目つけられてるみたいよ。気をつけたほうがいいわよぉ。」
凶嫁舞はちらと桜子の顔を見、つづいて「さん」づけで呼ばれた男たちの方を見やりました。京谷太郎、素行の悪さから悪太郎などと呼ばれていて、去年結局卒業できずに今年も高校3年生という男です。ひとつ年上ということと、見るからに不良の匂いぷんぷんさせているせいか、クラスメートたちは敬称をつけて呼んでいました。似たようなチンピラの取り巻きも多く、「しめる」といっては、クラスの中のちょっと目立つ男には、暴力をふるったり、脅しをかけているようでしたが、ほとんど会話をせず、何にも興味を示さないような凶嫁舞には、今まで彼らも無関心だったのです。
京谷太郎は、一瞬射すような視線を凶嫁舞に向けましたが、すぐに仲間たちとの会話に戻ったようでした。凶嫁舞はかぶりをふると、デイパックを背負い、苦笑をもらしました。
---俺も目をつけられるようになったってわけか。---
桜子は不審そうな表情で凶嫁舞を見ていましたが、彼が教室から出ていこうとすると、あわてて後を追いかけてきました。
「送ってってくれる?」
彼女は、凶嫁舞が土曜日にはバイクで通学してくることを知っていて、毎週タンデムシートに乗り、ちょっとしたスリルを味わうのを、秘かな楽しみにしていました。
校門を抜け、グラウンドと米軍キャンプの間の細い道を通り、ちょうど校舎とは基地をはさんで反対側にあるバイクショップに二人はやって来ました。カワサキW-1だのメグロ、陸王といった旧車ばかり扱っているヴィンテージショップです。
ご他聞にもれず、ここ岡山県でも三ナイ運動は盛んで、バイク通学は認められていなかったので、凶嫁舞は毎週この店にバイクを預かってもらっていたのです。
「ぉおぅ、今、帰りかい。」
店の奥でホンダドリームをいじっていた店主が、二人に声をかけてきました。
「おっちゃん、お世話さまぁ。」
凶嫁舞は店の前に展示してあるかのように置いてあった、ヤマハTX650にキーを差し込みました。
「おお、イイってことよ。お前さんのTXなぁ、欲しいって客が二人来たぜ。一人にゃ、こっちのメグロ売りつけたし、もう一人はTXさがしてやる段取りつけたし、そこに置いといてもらうと、商売繁盛ってもんよ。」
ヤマハTX650。秀逸なヤマハデザインの中でも、その流麗さでは、一歩も二歩も抜きんでているといわれるバイクです。バーチカルツイン650cc、奇をてらったトコロが微塵もなく、流れるようなタンクライン、あるべきところにあるシート、直立したエンジンが空冷フィンの美しい輝を放っています。時代は水冷、高出力エンジン、レーサーレプリカモデルといった方向に流れ、TXも時代の奔流には勝てず、既に旧車の仲間入となっていました。
凶嫁舞はバイクに跨がり、キックペダルを引きだすと、ひと呼吸おいておもむろにペダルを蹴り下ろしました。たくみなアクセルワークで、TXはなんのためらいもなく呼吸を始め、ずどどどどっ、と爆音を響かせます。桜子はこの瞬間が好きでした。日ごろ視点の定まらない表情をしている凶嫁舞が、一瞬見せる得意げな眼差し。ど〜だい、と言わんばかりの口元の笑みがたまらなく好きでした。彼女は凶嫁舞に手渡された、ショウエイのジェットへルを被り、セーラー服のスカートの裾を気にしながら、ホントはたいして気にならないんだけど、タンデムシートに跨がり、彼のカラダに腕を回しました。
凶嫁舞は背中に押し付けられる彼女の胸の柔らかさに、アライのジェットへルの奥で、ちょっと頬を上気させながら、TXをスタートさせました。
ずどどどどどおぉぉぉ〜っ。
よく整備されたバーチカルツインは独特の音をまき散らし、国道を闊歩していきます。電車の駅にして4つ分、倉敷市郊外の彼女の家まで、約50km、時間にして40分弱。のろのろ走るクルマを抜き去り、自分がこの道路の支配者であるかのように、縦横無尽に駆け抜けていく、彼と彼のTXと自分が渾然一体となる瞬間でもありました。桜子は凶嫁舞と『つきあっている』っていう状況でもなかったし、好きなのかどうかもよくわからなかったけれど、それでもこのひとときは一週間のうち、生きてることを自覚できる至福の時のような気もしていました。
+++++
メタルパッドがディスクローターを擦る音とともに、至福の時は終わりを告げます。彼女の家の前で、TXはゆっくりと速度を落とし、やがて静かに停止しました。
「…ありがとう。じゃ、また来週、学校で…。」
ヘルメットを脱ぎ、凶嫁舞に手渡すと、桜子は長い髪をかきあげ、彼がヘルメットをタンデムシートに固定しているのを見ていました。
「それじゃ…。」
と、凶嫁舞が言いかけたとき、桜子は不意に彼の唇に自分の唇を押しつけていました。なんでそんなことをしたのか、自分でも理解できませんでしたが、とにかくそうなってしまったのです。
「…ご、ごめん、きょうかまぃ…じゃ、さよならっ。」
慌てて庭木戸を押し開き、桜子は家の中へ駆け込んで行きました。凶嫁舞はバイクに跨がったまま、何が起こったのか、理解できず呆然としてましたが、カラダは正直で口元がしまりなくにやけてくるのが、わかります。彼は、首をぶるるっと振ると、慎重にTXをスタートさせました。
+++++
凶嫁舞の家は倉敷市内にありました。彼の両親は、彼が幼いとき死に別れ、兄と二人で暮らしています。幸い彼と彼の兄、凶嫁舞謙信には、時代の波に乗った才能があったのか、最近流行りのコンピュータプログラマとして、生活に困らない、というよりかなりの収入があり、市内の一軒家を維持することも困難ではありませんでした。
彼がTXをガレージにしまっていると、兄が出てきました。
「また、出かけるのか、信玄。」
兄、謙信は信玄より体格もよく、信玄が170cm弱なのに対して、180cmを越え、がっしりした印象です。信玄が答えずにいると、
「もみじ屋へ行くんだったら、バイク屋によってニンジャの部品もらってきてくれよ。」
もみじ屋というのは、このへんのバイク乗りが集まる喫茶店で、信玄もよくたむろっているところです。
「え、ニンジャ壊れてるの?」
「はっは〜、先週回しすぎてバルブジャンプしちゃってな。そゆわけだから、ニンジャには乗っていけないぞ、よろしくな。」
ニンジャとはカワサキの900ccのバイクのことで、映画トップガンの中でトム・クルーズが乗っていたヤツです。
謙信は大きく背伸びをすると、プログラムのバグ取りの最中だったのか、何行にも渡って赤線を引いた連続用紙をめくりながら、さっさと家の中へ入っていきました。
「うへぇ、こんな重たいバイク乗らね〜よ。」
兄には聞こえないよう、小声で信玄は呟きました。
+++++
もみじ屋は元々バイク好きなマスターが細々とやっていた店だったのですが、おりからのバイクブームと、隣にバイク屋ができたせいで、いつのまにかライダーが集まるようになったのでした。客層は大きく3つに分類されていて、凶嫁舞と同年齢の高校生たちと20代の若い会社員や大学生、それから30代の中堅サラリーマン、そして40オーバーのおっさんたち。それぞれにグループが自然にできあがっていて、お互いにはあまり干渉しない図式になっていました。排気量による免許制度もあって、『坊や』と呼ばれる凶嫁舞たち高校生や20代の『若増』はおおむねニーゴーやヨンヒャクのバイクがメインで、200km/hオーバーしたとか、どこそこで100km/h出たとか、そういう話題が中心だったし、30代の『舎弟』はサーキットやレースに話のハナが咲いていたし、『おっさん』たちは旧免許制度の恩恵でオーバーナナハンや伝説のヒトになりかかっていたので、お互い話が通じにくかった面もあったのかもしれません。
凶嫁舞も初めてこの店を訪れたとき、TXに乗っていったせいか、どのグループにも溶け込めず、それ以来ヨンヒャクに乗っていくことにしていました。
その日の夕方、もみじ屋に行くと、めずらしくグループに分かれておらず、皆で何かを騒いでいます。
「…ほいでよぉ、俺のRGガンマ、メーターレッドまでつっこんでるのに、離されてくんだよぉ。」
「そ〜だな、だいたいメータ読みで150km/h以上で3番目のコーナー突っ込んだのに、いとも簡単にかわされるんだぜ。」
「わしなんか、帰りの直線で220km/hだったのに、ひょいとぬかれたよ。」
凶嫁舞はニコニコして聞いているマスターにアメリカンを注文して、RZ250に乗る少年の隣に座りました。
「…なぁ、なんの話だ?」
「あれ、知らないのか?ここんとこ例の桃太郎峠にバカっ速いBMWが出るんだ。」
「???? BMW? んなん、ツーリングバイクだろ。」
「いや、それがさぁ、R80とかいうやつで、すげ〜んだよ。ケンタのボルドールが置いていかれたって話だもん。」
ケンタというのは、この辺の走り屋の間では一番と噂されていて、ボルドール、ホンダCB750Fにモリワキ集合やらCRキャブを装着していて、実馬力120psは超えているらしいマシンに乗る男のことです。ただ、凶嫁舞はいっしょに走ったことがないので、その実力の程は少々疑っていましたが。
「桃太郎峠だろ、下から上まで速いのか?」
「どこで走っても、ぶっちぎりらしいんだ。下りだと勝負にもならないってさ。」
誇張されてるにしても、かなり速いBMWのようです。凶嫁舞はカウンターに置かれたアメリカンをひとくちすすりました。
桃太郎峠。正式には、埴生山周回路と呼ばれます。かつて岡山で国体が開催されたときに、天皇陛下の植樹祭のために作られた道路で、その後観光地化する予定で、「桃太郎の里」という一大プロジェクトを県が打ち立てたまではよかったのですが、元々何もない場所で商売になるはずもなく、また埴生山を一周するだけで、何処へも抜けられない道路だったせいで、結局プロジェクトは雲散霧消、くねくねと曲がる道だけが、真新しい舗装のまま残っているというところでした。そのうちその周回路に次第にバイクが集まるようになり、いつのまにか桃太郎峠と呼ばれるようになったのです。大小さまざまなコーナーが林立し、高速コーナー中心の上り始めから頂上付近の低速の切り返しまでバラエティに富んだ全長20kmのコースで、凶嫁舞もよく走りに行きます。この周回路の人気が高いのは、全線一方通行でぐるっと山を一周できることで、タイム計測ができることでした。もみじ屋にも壁に歴代タイムが貼りだしてあり、その一番上の名前がケンタでした。
「それで、そのBMWはいつ出てくるんだ?」
「あっは、凶嫁舞、勝負するつもり?やめときなって、ボルドールが追いつかないんだからさ。」
「…いや、見たいじゃないか、どんな風なのかさ。」
「あぁ、まあね、見るだけでもおもしろいかもな。でも、いつ来るかわかんねぇらしいんだよね。夜中だったり、平日の昼間だったりさ。一説によるとセッティング出してるんじゃねぇかってハナシだけどさ。」
その後、店内はBMWがどんな改造をしてるのかという話題になり、結局正体不明のまま、興奮だけが残りました。
一人去り、二人去り、店内に凶嫁舞以外には、『おっさん』連中とマスターだけになった時、『おっさん』の一人が彼に声をかけました。
「なあ、凶嫁舞、お前BMWとはヤルなよ。」
凶嫁舞は夕食代わりに食べていたミートソースをたいらげたところで、3杯目のコーヒーを飲んでいました。
「あいつはなぁ、なんつうか、普通のバイク乗りじゃねぇんだ。…そう、人間ばなれしたっていうか…。」
凶嫁舞は怪訝そうな顔をしたまま、『おっさん』の方に向き直りました。
「凶嫁舞、お前さんなら、追いつくかもしれん。でもなぁ…。」
『おっさん』は何かを思うような顔つきのまま、黙りこんでしまいました。
「だいじょぶっすよ。俺はヤッたりしませんよ。自分のペースをみだすようなことは、しませんて。」
+++++
この時期、午後9時を回ると、桃太郎峠を走るものは皆無です。夏の暑いさかりには、それこそ多くのバイクで賑わうのですが、秋も深まった10月半ばすぎともなると、バイクはおろか4輪の走り屋さえも影を潜めてしまいます。
凶嫁舞は峠の入口、皆がパドックと呼ぶ駐車場にバイクを停めました。エンジンの音が消えると、肌寒い風が吹きつけぶるるっと身震いしました。駐車場には何本かの照明灯があって、うすぼんやりとしていますが、道路の方は、きついコーナーに何箇所か照明があるだけで、ほとんどが真暗い闇の中に吸い込まれていました。そのBMWが来るかどうか判りませんでしたが、この道を走ったであろうBMWのことを考えると、ここまで来ずにはいられなかったのです。
彼は、暗い照明の中に浮かび上がる自分のバイクを眺めました。
ヤマハFZR400RR。前傾4気筒エンジン搭載、EXUP装備、6速クロスミッションの、F-3レース用ホモロゲマシン。走ることに徹したそのマシンは、一人分の乗車スペースしかなく、やさしいデザインとは裏腹な、硬派なライディングを強要。今のところ彼のお気に入りでした。
自分のマシンを見るのにも飽きて、遠い街の明かりをぼんやり眺めていたとき、不意に音は聞こえてきました。ツインエンジン独特の鼓動。
来る。
凶嫁舞は直感的にそう思いました。FZRのキーを回し、セルスタータを回し、インライン4に火を入れます。スロットルを煽り、発売されたばかりのFCRキャブが正しく吸気音を発生させるのを確認すると、バイクに跨がり駐車場の出口へFZRを向けました。ツインエンジンの鼓動音は次第に大きくなり、やがて、最初のコーナーを立上がり、凶嫁舞とFZRを、そのライトが照らしだしました。
そしてツインエンジンの鼓動音は、駐車場の入口、凶嫁舞の正面で止まりました。彼は落ち着いてFZRのヘッドライトを点灯します。強力なハロゲンランプの光軸に現れたのは…。
BMW R80だ。
BMWは、こんな時間に出現したもうひとりのライダーに驚いたのか、確認するかのように、凶嫁舞の方へ顔を向けています。そして、2、3度スロットルを煽ると、やおら発進しました。凶嫁舞も遅れずにやや高めの回転でクラッチミート。この駐車場から次のコーナーまでは、最高速が出る直線です。ゼロ発進加速にはやや不利なクロスミッションがもどかしい。BMWは容赦なく加速しているようで、少しずつ離されていきます。凶嫁舞FZRが、ようやく最初の右コーナー入口に到達したときには、BMWはコーナーを脱けようとしているところでした。6速全開から、軽くブレーキング、シフトを1速落し、思い切りよくバンクさせます。時速は150キロ。温まりきっていないタイヤが路面をつかみそこね、FZRは車体をズルズルと泳がせ、多少ベストラインからは外れましたが、凶嫁舞は気にせずアクセルを開けていきます。前を確認するとBMWはストレートの加速で離しはしたものの、この先の高速S字の切り返しに備え、早めにアクセルを戻しているようです。
やたっ。
凶嫁舞は、BMWが予想通りの挙動を示しているのに、ほくそえみました。シャフトドライブ特有の癖で、右コーナーでは、バンクしようとする動きが強く、左コーナーではその逆になるため、全開のまま高速の切り返しをクリアすることはできないだろうとふんでいたのです。
凶嫁舞はハーフスロットルから一気に全開にしました。FZRに装着された、オーヴァレーシングのエキゾーストが雄叫びを上げ、燃料タンクの下に配置された、FCRキャブレターが狂喜の声を狂わんばかりに発します。猛然とダッシュしたFZRはBMWに食らいつきそうです。凶嫁舞は大きく身体を左側に落とし、全開のまま切り返し、もたついてるであろうBMWのイン側に飛び込もうとしました。しかし、一瞬BMWの方が速く、凶嫁舞FZRの前を横切っていきました。ライトに照らし出されたBMWのテールランプの下に、大文字の「R」に何やらバイクのような絵が書いてあるエンブレムがついています。ちらっと見えたエンジンヘッドは、なじみのあるBMWの桃尻ではなく、ごつごつとした鈍いアルミの光沢。背後から見る、時折街灯に照らし出されるそのシルエットも、凶嫁舞の知っているBMWのものとは違うようです。水平対向エンジンのため、左右に張り出したシリンダーは通常よりずっと上に位置し、やや角度がついているようです。
レーシングBMW?
BMWが耐久レース復帰のために作ったといわれる幻のR100Rか?
BMWのライダーは、そのマシンに相当手慣れているらしく、大きくハングオンしながら、コーナーを駆け抜けて行きます。凶嫁舞はいっこうに縮まらない差にいらついてきました。
頂上付近になると、細かいコーナーが連続し、パワーよりも軽いハンドリングが有利になります。
ここで行くしかないっ。
頂上手前3km地点で凶嫁舞はそう思い、突っ込みでかわすべく、コーナーの奥までブレーキングを遅らせました。BMWも凶嫁舞の意図に気づいたのか、同じようにブレーキを遅らせています。
しめたっ。シャフトの弱点が出るはずだっ。
案の定、BMWのリアタイヤはホッピングし、挙動を乱したかに見えました。けれど、BMWはそのまま何事もなかったかのように、FZRの前でコーナーに進入していきます。あまりに鮮やかでした。その瞬間、凶嫁舞の闘志の半分は失われたのかもしれません。その後は、BMWの後ろにくっついていくだけが精一杯で、そのまま頂上の直線まで、FZRはBMWに引っ張られるように走りつづけるだけでした。
頂上の直線は、緩い上り勾配になっていて、ちょうど駐車場入口があるあたりが、その頂点になっていました。上りきるまで先が見えないので、普段は全開で駆け抜けることはないのですが、BMWはアクセルを戻す気配がありません。凶嫁舞もぴったり後ろについたまま車速を押し上げていきました。BMWが坂の頂点でジャンプし、凶嫁舞も続こうとした刹那、駐車場からクルマが出てきたのです。それは、間延びした時間でした。凶嫁舞は咄嗟にブレーキをかけ、前後フルロックしたままのFZRをコントロールし、懸命に衝突から逃れようとしました。マヌケなクルマの運転手は大きく口を開けたまま、凶嫁舞を見つめています。
だめだっ。間に合わないっ。
FZRはクルマの左フェンダーに衝突し、凶嫁舞は空高く放り上げられました。クルマのボンネットが見え、ついで星空が見え、そして冷たいアスファルトに叩き付けられました。
+++++
暗転。無限の暗転。
+++++
なぜか昼間の桜子を思い出し、その唇の感触が甦りました。気がつくと、まだ数秒もたっていないようで、慌てたクルマの運転手がドアを開け出てこようとしているところでした。凶嫁舞はゆっくりと頭をもたげ、立とうとしてよろけ、その場に座り込んでしまいました。
「大丈夫かい?」
運転手の声が虚ろに聞こえます。しかし、凶嫁舞の目は、数メートル先で停止しているBMWを一直線に見据えていました。BMWは安定したアイドリング音を響かせています。
どっどっどっどっどっ
そしてBMWのライダーは、とりあえず起き上がった凶嫁舞を見て、「ラッキーだったな」とでも言うように片手を上げ、ミッションの音もけたたましく、走り去って行きました。
「あれっ、あのバイク仲間じゃないのかい?」
運転手の声に、凶嫁舞は、ただ黙って首を振るばかりでした。
BMWの排気音はしばらく山にこだまし、そして次第に小さくなり、やがては聞こえなくなりました。晩秋の風は、つむじを巻き、冬の訪れを秘かに告げようとしていました。