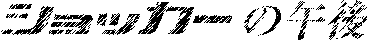
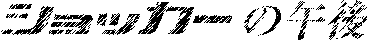
夏の日差しは万人に平等だな。
勝義はそう思いました。古ぼけた建屋の軒先で、青すぎる空を見上げながら。足元で新聞がかさかさ音をたてました。
彼は首を振り、通りの反対側の店先に視線を移しました。反対側の店は果物屋で、おいしそうな南国の果実が並んでいます。もう何日食事をしていないだろう。ああ、あのマンゴーはうまそうだなあ。マンゴー怪人っていたっけかな、ゾル大佐は恐かったな、ああ、博士の墓参り行かなきゃな、おかしな空想になってしまうのは、空腹のせいです。
彼が最後に食事らしい食事をしたのは、正確には2週間も前です。別にお金がなかったわけではありません。断食をしてるわけでも、もちろんありません。どういうわけか、この町のお店では買い物ができなくなってしまったのです。
この町に越してきたときから災難つづきでした。住民票の転入届は受理されないし、家のまわりを町の人達がとりかこんで、口汚なくののしります。せっかく仲間達と新しい生活を始めようと思っていたのに、勝義はちょっと不安になったのでした。
勝義の両親は、彼が小さい時に亡くなり、彼は16まで施設で育ちました。中卒で小さな印刷屋さんに就職しましたが、社内で窃盗事件があったとき、いわれのない疑いをかけられて、クビになってしまいました。おかげで人間不信に陥り、街をうろつき、すっかり不良になってしまったのです。そんなある晩、勝義はギャングにからまれてしまいました。いくら不良とはいっても、ギャングとは対等に立ち会えません。そのとき、ただ恐くて震え上がっていた彼を、マントをつけた紳士が救ってくれたのです。紳士はあっというまにギャングをかたづけてしまいました。白髪で、見た目はとても恐い感じでしたが、紳士は勝義に名刺を渡すと、「困ったことがあったらいつでもおいで」と、やさしく言ってくれました。名刺には、死神博士、株式会社ショッカーと書いてありました。次の日、勝義が名刺を持って会社を訪ねたのは言うまでもありません。
会社は全寮制で、制服支給、24時間勤務の3交代制、給料はおせじにもいいとは言えませんでしたが、同じような境遇の仲間がいて夜な夜な夢を語ったものでした。本社は東京丸の内にありましたが、本社勤務できるのは取締役だけで、一戦闘員の勝義たちは、地方の工事現場に勤務していました。入社して半年後、いよいよ会社は世界制覇に乗り出すことになりました。勝義たち戦闘員の中からも、何人かが選ばれ、改造人間として取締役になるものもいましたが、あいかわらず勝義は戦闘員のままでした。
社長は首領と呼ばれていて、ワンマン経営だったようです。時々、死神博士は勝義を食事に連れて行ってくれたのですが、よく愚痴を聞かされたものです。その経営方針の失敗なのか、ある時を境に会社が傾き始めました。なんでも、仮面ライダーという取締役が裏切り、勝義たちの会社を目の敵にして、次から次へと邪魔をし始めたらしいのです。仮面ライダーは取締役の中でも一番有能で、力もあったので、たちまち株式会社ショッカーは倒産寸前となってしまいました。勝義も何度かライダーと戦いましたが、ライダーパンチとかキックでその度、病院送りにされました。取締役が次々と倒され、いよいよ会社更正法か破防法摘要かという段になり、首領は最後の作戦を繰り出しました。世間を騒がしたサリンゲドンの新宿毒ガス作戦です。勝義たち地方社員はこの作戦に参加できませんでしたが、テレビでその惨劇を見た時、首領の恐ろしさに身が縮み上がったものでした。しかし、この作戦はライダーを倒すことには失敗し、結局首領はライダーに捕らえられて、会社は法人格を剥奪されて、社員はちりぢりになってしまったのです。
その後、残務整理をしていた地方社員の有志が新たに有限会社ゲルショッカーを設立し細々と営業しているらしいという噂は耳にしました。しかし、勝義は、取締役イカデビルとしてライダーに特攻をかけ自爆してしまった死神博士の思い出を胸に、まっとうな人間になろうと誓いショッカーの過去を隠して生活することにしたのです。けれども、世間はそう甘くはありませんでした。異臭騒ぎや、毒物混入事件があると、勝義の勤務先に刑事がやってくるのです。もちろん身に覚えのないことなんですが、勤務先で刑事やライダー少年隊にうろつかれては、仕事を続けることは困難になってしまいます。何度か職場を転々とした後、勝義はかつての同僚戦闘員に会いました。話を聞くとやはり同じような状況らしく、お互いの境遇を嘆きました。そんな苦しい日々に思い出すのは、楽しかった全寮生活のあの頃です。結局、社会に受け入れられない彼らには、行き先はそこしかなかったのかもしれません。勝義が、昔のつてを頼って、ゲルショッカーに入社したのは、テポドンが飛んだ年の冬のことでした。
ゲルショッカーもあいかわらず安月給でしたが、会社はパソコン激安販売が受けて、そこそこの収益を上げました。前回のショッカーのワンマン経営に懲りて、合議制で運営することにもしました。秋葉原に店舗を持っていたのですが、都会は家賃が高いので、地方に居を構えることになり、そうして勝義たちはこの町に引っ越してきたのです。ところが引っ越し当日から雰囲気は最悪です。購入した工場兼寮の周りを、町民がとりまき、ゲルショッカーは出て行け、ゲルショッカー許すまじのプラカードを掲げ、さながら、成田空港反対闘争のようでした。町役場に住民票の転入届を提出に行けば、報道陣がとりまき、そのあげく受理してもらえず、もう勝義は悲しくなってこみあげる涙をこらえることができませんでした。それでも、しばらくはなんとか我慢して、生活を続けたのですが、それは突然やってきたのです。
いつものように勝義たちが買い出しに行くと、店主が入口で通せんぼしています。「あの〜、入れてくださいな」と勝義が頼むと、店主はウィンドウの貼り紙を黙って指差します。そこには、ゲルショッカーには売りません、と書いてありました。驚いて、店主を見返すと、店主は首を振り、帰れと手で合図しました。勝義の同僚たちは何か言いたげでしたが、それを制しながら、別の店へと向かいました。だけど、その店にも大書した貼り紙が・・・。
町の有力者が言いくるめられて、音頭をとって始めたようでした。町中どこのお店に行っても、大きな黄色い貼り紙がしてあって、そこには、ゲルショッカーには売りません、もう、それは呪文のように繰り返されるのです。同僚たちは、口々に勝義に言いました。総会屋だって暴力団だってお買い物できるのに、なんで僕らには売ってくれないんだ。僕らが何するって言うんだ。たしかに以前事件を起こしたかもしれない。だけど、首領は捕まっちゃったし、取締役はみんなライダーキックで爆死しちゃったじゃないか。僕らは何もやってないし、何もやらないよ。また、ある同僚はこうも言います。そんなに、何かしでかすっていうなら、やってやろうじゃないか、また改造人間で暴れてやってもいいんだ。憤る彼らに、勝義は静かに語りました。
「いや、それは違う。かつて死神博士は、僕に言ったんだ。わしらはこんな風にしか生きられないけど、おまえ達は、世間に胸張って生きてもらいたい。けして、くじけるんじゃないよ。そう、言ったんだ。もし僕らがここで騒動を起こしたら、僕は博士に顔向けできないし、それは奴等の思うつぼだ。とにかく、ここが我慢のしどころだ。つらいだろうが耐えてくれ。」
こうして、勝義たちは座して待つことになったのです。
僕は何を待っているのだろう。 ぼんやり通りを眺めていた、勝義はふと思いました。何か事態が改善されるのだろうか。同僚たちは空腹をまぎらわすために、さっきから堂々巡りのしりとりを続けている。かめんらいだあ、あ、あまぞんらいだあ、あ、ありがばり、り、りとるきんぐ、ぐ・・・・。
同僚が拾ってきた朝日新聞が足元で、かさかさと音をたてました。北朝鮮に援助を。一面の題字が踊っています。ミサイルを飛ばす国には援助するのか・・・。彼らには彼らの考えがあるんだろうな。
・・・き、きんぐぎどら、ら、らいだあまん、ん、ん、ん、ん・・・
勝義の思いも堂々巡りを続けます。施設のこと、ショッカーのこと、ライダーのこと、首領のこと、死神博士のこと・・・。
そのとき、勝義は、わかったような気がしました。死神博士がライダーに自爆覚悟で攻撃をしかけたわけが。博士は勝つつもりなどなかったんだ。最初から死ぬ気でいたのだ。博士にとってライダーと戦って爆死することこそが、彼の願いだったのだ。決して勝ってはいけない。最初から負けることが重要だったのだ。博士が最後の決戦に向かう前に、勝義に見せた、微笑みの意味はそこにあったのだろうか。
もう、勝義にはよくわからなくなりました。自分達がなにもので、どこへ行こうとしているのか、どうしたらいいのか、考える力もなくなりました。そうして深い哀しみが、ただ、ただ彼を取り巻くのでした。
そうしてそれからも、夏の日差しは、万人に等しく降り注ぐのです。