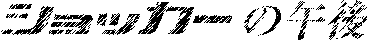
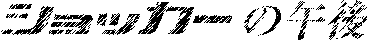
「勝手なことをされては、いい迷惑ですっ。」
ショッカー東京丸の内本社の医務室で地獄大使は声を荒げました。
「まあ、待て。やってしまったものは仕方がない。それに大佐の言うように、脳改造をしてから帰してやれば、こっちの都合のいいようになるやもしれんしな。」
首領は、大きな体を揺すりながら、話しました。
「脳改造には危険がともなう。失敗した場合のことも考えているのかね、大佐。」
と、死神博士。ゾル大佐は背中の治療をしてもらいながら、不敵な笑みを浮かべたまま、押し黙っていました。
「ともかく、今回の件は大佐に一任することにする。」
首領の意見は絶対です。なにか言いたそうでしたが、渋々、地獄大使はひきさがりました。
治療を終え、オフィスへ向かう途中のゾル大佐を、エレベータの前で、その地獄大使が待ちかまえていました。
「大佐、現場へ行ったはずのスネーク部隊が戻ってこないのですが。」
「ふん、スネーク部隊なぞ見かけなかったな。おおかた、どこかで男でも漁っておるのだろうが。」
うそぶくゾル大佐に地獄大使はつめよりました。
「現場にはマリバロン閣下も行ったはずです。今、部下を現場へ送りました。報告次第では、覚悟を決めてもらいますよ。」
「知らんといったら、知らんっ。」
地獄大使の手をふりはらうと、ゾル大佐はちょうどやって来たエレベータに乗って去って行きました。
部下からの報告は、意外なものでした。折からの雨が洗い流したのか、現場にはなんの痕跡も残っていないというのです。そんなはずはない。あのマリバロン様が、大佐の愚かな行為を放っておくはずはない。現にゾル大佐は傷を負っていた。拉致するときに抵抗され熱湯をかけられたと言っていたが、生身の人間が改造人間に危害を加えるのは無理だ。疑いをもった地獄大使は、脳改造手術の準備をしていた死神博士をつかまえて、たずねました。
「……お前さんの疑念はもっともだ。たしかにあの傷は、ただの火傷じゃない。それにあばら骨も何本か折れていたようじゃ。しかし、わしに言えるのはそこまでじゃ……。」
ますます疑いは深まります。地獄大使はもう一度部下を呼び、秘かな指示を与えました。雨はすっかり上がったようでした。
+++++
長い眠りから覚めるとき、ひとはどう感じるものなのでしょう。気持ちのよい目覚め、あるいは悪夢からの解放。彼女の目が覚めたとき、そのどちらでもありませんでした。下腹部から背中へかけて鈍痛が走り、からだじゅうを炎で焼かれる感じがしたのでした。日頃の用心のせいで、彼女は目が覚めても、身動きひとつしませんでした。まず耳をすまし、次に薄目を開けて、周囲を観察しました。どうやら、どこかのアパートのようです。ひとりの男がむこう向きに座っています。パソコンを操作しているようでした。
「目が覚めたようだね。」
不意に男は振り向きもせず、話しかけてきました。
「ああ、何も話さなくてもいい。君のことは知っている。」
わたしもあなたのことを知っているわ、仮面ライダー。
+++++
ライダーが事件のことを知ったのは、あの晩、遅くなってのことでした。ショッカーを裏切ったライダーは、その強さから、今でもショッカー内部にシンパがいて、彼らが内通者として協力をおしまず、時折連絡が入るのですが、その晩の電話はちょっと違いました。ライダー少年隊ではなくタチバナモータースの方へ、ショッカーが弁護士を誘拐しようとしていると、いつもの戦闘員からではなく、女性の声で電話があったというのです。おやっさんは、罠かもしれんとライダーを止めましたが、ライダーは胸騒ぎを覚えて、雨の中現場へ向かいました。住宅街の一角でサイクロン号を停め、ライダーは注意深くあたりを探ります。すでにスネーク部隊戦闘員の死体は、消滅しており、現場には裸の女性が倒れているだけでした。
「しっかりしろっ。」
抱え起こしたときに、ライダーは驚きました。ここ数日テレビでその顔を何度か見かけた、ショッカーのマリバロンだったからです。
「むぅ?」
ライダーはいぶかしく思いましたが、マリバロンの体は冷えきっていて、脈はかろうじてある程度です。脈をとるとき、彼女の首筋に製造番号が打たれていることに気づきました。
「……改造人間。」
忌まわしい言葉が彼の口からこぼれました。雨は次第に強さを増し、世界中を押し流すかのように降り続いていました。
+++++
「まだ動かないほうがいい。いくら強化細胞とは言っても、それだけの傷だ。3日くらいでは元に戻らない。」
「3日?3日も経ってしまったの?」
マリバロンは慌ててベッドから出ようとしました。けれども、バランスをくずして、床に倒れ込む寸前のところを、ライダーに抱きかかえられました。温かい。マリバロンはそう感じました。改造人間同士の接触は、ふつう無生物のような冷たい印象しか与えません。しかし、彼女はそのとき、たしかに温かな感じがしたのでした。
「罠だとは、考えなかった?」
ベッドに再び横になり、彼女はたずねました。ライダーは、一瞬片方の眉をつりあげましたが、少し間を置いてから、無表情に返事しました。
「罠かもしれない。今もそう思っている。」
二人とも、そのまま押し黙り、何も聞こうとはしませんでした。狭いアパートの無限の時間だけが、ゆっくりと流れていくような、そんな気がしました。
マリバロンとライダーは同時期にショッカーで活動したことは、ありません。彼女が入社したとき、すでにライダーは辞職していましたから。最強の改造人間で優秀な取締役だったことは、死神博士から聞かされましたが、数々の妨害工作に、マリバロンは、少々やっかいな敵だなと思っていただけでした。ゾル大佐暴走の報告を地獄大使から受けたとき、スネーク部隊だけでは、制止できないと、彼女にはわかっていました。後々不利になるかもしれないとは思いましたが、最悪の事態を避けるため、マリバロンはライダーに連絡をしたのでした。
結局、大佐を止めることはできなかった。あげくにこのざま。彼女は急にくやしくなり、涙をこらえることができませんでした。あとから、あとから、大粒の涙があふれてきて、頬をつたいます。しまいには声をあげて泣き出しました。ライダーはちょっと驚きましたが、優しく彼女の髪を撫でてあげました。
最後に泣いたのは、いつのことだったのでしょう。マリバロンは幼い時に両親に捨てられ、親戚のうちをたらい回しにされてきました。どこへ行ってもやっかいもの扱いで、いつしか彼女の心には鉄の壁が築かれていたようです。鉄の壁の心は、どんな障害も乗り越え、彼女をショッカーの取締役にまで押し上げましたが、反対に心は安住の地を失い、休まることはなかったのです。こうして涙が止まらないのは、今まで強固に閉じ込めていた心が解放されたからなのでしょうか。マリバロンにはわかりませんでした。ただ、涙がこんなに気持ちのいいものだと、思い出したのはたしかでした。
+++++
「なにいっ。死んだあっ!?」
フロア中に響き渡るような声で、ゾル大佐は叫びました。報告した科学研究員はちぢみあがりました。
「脳改造に耐えられなかったのだ。」
見かねた死神博士が答えました。しかし、いらつくゾル大佐はさらに語気を強めて吠えます。
「あれから10日も経っているんだぞ。世間もそろそろ騒ぎ出す。だいいち首領になんて報告すればいいんだっ。」
「首領に報告する必要はない、ゾル大佐。」
いつのまにか入口に立っていた地獄大使が言いました。
「あなたの今回の独断先行は、大間違いだったのだ。きっちり責任はとってもらいますからね。首領には、私から報告します。」
そう言い捨てると、地獄大使は金色のマントをひるがえし、さっさと部屋を出て行ってしまいました。くそう、あのエジプト野郎め。マリバロンがいなくなったのを幸いに、でかい面しやがって。地団駄を踏んで、ゾル大佐は悔しがりましたが、彼にはもうどうすることもできないのは、明らかです。ゾル大佐はひきずるような足取りで、自分のオフィスに戻っていきました。
私服の戦闘員がひとり、あたりをうかがいながら地獄大使のオフィスへ入っていきます。
「誰かに見られなかったろうな。」
小声で地獄大使が念を押すと、戦闘員は黙ってうなずきました。
「マリバロン様の居場所、確認できました。」
そう戦闘員が話すと、地獄大使は、考え込む表情になりました。
「救出に行かれるのですか。」
戦闘員の問いには、地獄大使は答えず、逆に質問しました。
「この件を他に知っている者は?」
「最初の発見者は、指示通り始末しました。他に知っている者は、いません。」
返事を聞くと、地獄大使は目にも止まらぬ速さで、剣を抜き、戦闘員の胸を刺しました。戦闘員は声を上げる間もなく、しゅんと鈍い音をたてて、蒸発してしまいました。
「マリバロン、生きていたのか……。」
地獄大使は、そうつぶやくと、深い思考の底に潜っていったのでした。
+++++
「わたしには、会社を裏切ることはできないわ。あなたのようにはね。」
ベッドの中でマリバロンが囁きました。
「そうか……。」
彼女の背骨を指でたどりながら、ライダーは呟きました。
「このまま放っておけば、ショッカーは暴走してしまう。いいえ、もう暴走し始めているのかもしれない。誰かが停めなければならないのよ。すでにひとつ、道を間違えてしまったわ。死神博士は、後戻りはできないって言うけど、きっと正しい道があるはず。わたしにはそれを見つける責任があるのよ。」
ライダーは何も答えず、黙って聞いていました。
+++++
しばらく好天気が続いていたのに、今朝は昨晩からの雨が、まだ降り続いていました。窓から表を見ていた地獄大使は何か決心するように頷くと、オフィスを出ました。ロビーまで降りたところで、後ろから呼ぶ声がしました。死神博士です。
「こんな雨の中、何処かへ出かけるつもりかね。」
地獄大使は、それには答えず、マントのフードを深く被り直しました。
「ふむ、老いぼれには用はないか……。」
雨の中を小走りに出て行く地獄大使の背中を見送りながら、死神博士はひとりごとのように呟きました。
+++++
「ほんとにもう大丈夫なのかい。」
おやっさんは心配そうに、彼女に聞きました。
「ええ、たいへんお世話になりました。おかげさまで、具合もよくなりましたので、戻ることにします。」
「タケシももうすぐ帰ってくるはずだ。それまで待ってたらどうだい。」
「いえ、タケシさんにはよろしくお伝えください。」
レインコートのフードを立てると、彼女は一礼して歩き出しました。おやっさんはまだ心配で、タケシの野郎が帰ってこないかと、店の前で通りの向こうを見渡しています。そぼ降る雨は、止む気配もなく、新宿の街を濡らしつづけていました。
+++++
地獄大使が新宿の駅に降りたときも、まだ雨は降っていました。休日の早朝のせいか、人影はまばらで、車もほとんど走っていません。高層ビルが雨のなか、ぼうっと霞んで見えました。地獄大使はビルの影に隠れると、何かを待ち伏せるかのように、じっと息をこらして気配を消していきました。
+++++
マリバロンは駅前まで来たところで、足を止めました。改造人間だけが感ずる、異質な空気を嗅ぎ取ったからです。それは、通りの反対側から感じられました。
「マリバロン様、恋人ごっこはもうおしまいですか。」
「その声は地獄大使ね。わたしを迎えに来たの。」
「いいえ。あなたを迎えに来たのは、地獄からの使者ですっ。」
そう言うと、地獄大使は金色のマントを広げ、空高く飛び、異形の戦士となってマリバロンに襲いかかってきました。巨大な甲虫の姿になった、地獄大使は、マリバロンの胸めがけて、その角を突き出してきました。
「なるほど、そういうことなの。地獄大使、地獄に落ちるのはあなたのほうよっ。」
マリバロンは駅前の高架から、一気に飛び降りました。その後を、ぶうんという羽音をたてながら、巨大な甲虫が追います。古びた雑居ビルが取り囲む狭い空間で、マリバロンは甲虫と向き合いました。ぶうんぶうんと羽音をたてながら、甲虫は右に左に揺れています。マリバロンは、真っ直ぐ甲虫を見据え、動きません。しびれを切らした甲虫がいったん後ろに引き、勢いをつけて前へ出ようとした刹那、マリバロンも飛び出しました。彼女の体が凶悪なヘビ女の姿へ変わり、大きく開いた顎の牙で、甲虫の腹部を切り裂きます。巨大な甲虫から、黄色い体液が飛び散りました。
「ぐお、なかなかやりますね。マリバロン様。」
彼はもんどりうって、ビルの壁に体をいやというほど叩きつけてしまいましたが、2度目の攻撃を避けるため、傷口を押さえて、かろうじて立ち上がりました。けれども、2度目の攻撃はありませんでした。なぜなら、マリバロンはすでに、人間の姿に戻って、地面にうつ伏せに倒れていたからです。まだ、怪我が完全に治りきらないうちに変身したので、エネルギーを使い果たしてしまったのです。
「うふふ、運は私の味方のようです。」
彼がとどめを刺そうと身構えたとき、何者かが近づいてくる気配を感じました。
「うぬぅ。」
まだ視界にとらえることはできませんでしたが、その強烈な気配は、どうやら、仮面ライダーのようです。
「もう少しだというのに、くそ。」
手負いの状態でライダーと闘えば、地獄大使のほうがやられかねません。彼はぶうんと羽ばたくと、その場を離れました。
+++++
冷たい雨がマリバロンの背中を叩きつけていましたが、ライダーが側に立っているような温かな気配を感じました。でも、それはほんの短い間で、彼女の意識はすうっと冷たい闇に閉ざされ、同じように彼女の肉体も消滅していきました。
ライダーの頬をひとすじの滴が流れたような気がしましたが、それは涙だったのか、それとも雨粒だったのか、ライダー自身にもわかりませんでした。